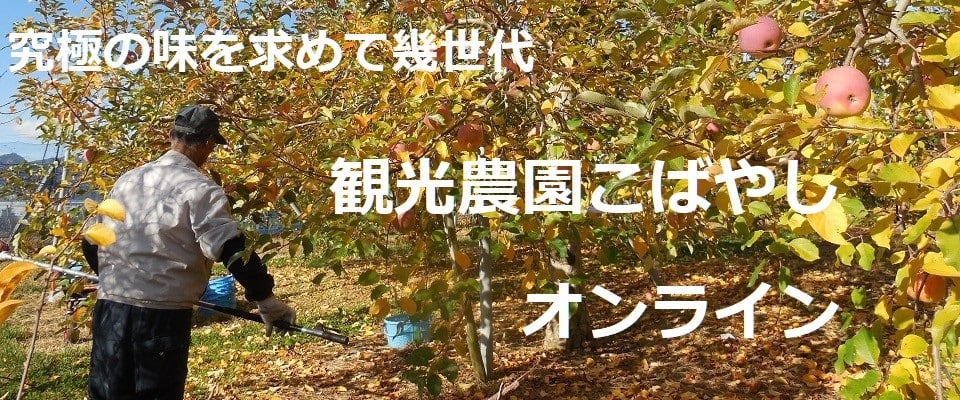おいしさのヒミツ
果物がおいしくなる!信州の気候
観光農園こばやしの畑のある長野県東御市は、年間降水量の少なさが全国でトップクラス、昼夜の寒暖の差が大きい、という特徴があります。
それぞれが果物の生育にどのような影響を及ぼすのか説明します。
年間降水量の少なさがトップクラス
長野県は降水量が全国で一番少ない県であり、長野県の中でも東御市は特に雨が少ない地域です。
雨の少ない地域は土壌の養分が水に流されてしまうことが少なく、果物に養分を送りやすくなります。
さらに、降水量が少ないということは、日光を多く浴びているということにも裏付けできます。日光は果物が育つのに必要な養分の一つなので、おいしい果物ができる理由の一つだと考えられます。
雨が少なすぎるのも果樹に悪い影響を及ぼすので、観光農園こばやしの圃場では灌水設備を使用し、必要な時に灌水を行うことで果物の生育にちょうどいい環境を作っています。
昼夜の寒暖の差が大きい
果実は昼の暖かい時間に光合成を行い、糖分を作り出すというメカニズムがあります。そして夜になり気温が下がることで、昼の間に作った糖分を果実の中に閉じ込めているのです。
この繰り返しによって甘く、高糖度の果物が出来上がります。
代々続くこだわりの栽培
観光農園こばやしの農園は、戦後の食糧増産の頃から現在まで果物栽培が続いています。
(果樹以前も農家で、総じてみると100年以上前から農業に携わっています。)
初代が現在の農園にリンゴを植え栽培を始めました。
その後二代目が農業高校卒業後、跡継ぎとなり、ブドウやモモ、クルミといった様々な果物を増やし直売所も開店させました。そのまま60年以上栽培を続け、現在は三代目にその経験と技術を指導しています。
三代目は県農業大学校果樹実科で果物についての最新技術を学び、卒業後はそのまま跡継ぎとなりました。
現在は二代目の指導の下、大学校で学んだ新しい技術も取り入れながら年々改良を重ねています。
代々続く農家によるこだわりの栽培法と経験により、高品質な果物ができます。
味を重視した栽培
観光農園こばやしでは果物の大きさとおいしさをよくするため、樹にならせる果物の数を少なくしています。
果実は、葉っぱが光合成することにより作り出される養分をもらって成長しています。
樹にならせる果実の数を少なくすることによって、果実ひとつひとつの養分の量を増やしているのです。
たくさんの養分をもらって成長した果物は大きく、おいしい果実に成長します。
さらに、観光農園こばやしではよりおいしい果物を作るために、過度な葉摘み作業を控えています。葉摘みはリンゴの着色を良くするために行う作業ですが、やりすぎると果実の糖度が下がるという研究結果があります。
葉摘みを控えることでリンゴの着色は悪くなりますが、その分味がよくなります。
観光農園こばやしの栽培方針は見た目より味です!
新鮮を届けるこだわり
観光農園こばやしの農作物はすべて必ず朝採りにこだわっています。
日中の暑さで水分が飛ばされる前に収穫を行い、みずみずしく新鮮な状態のうちに収穫できます。